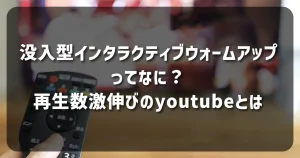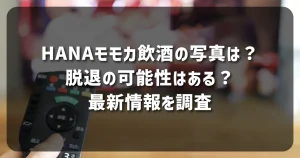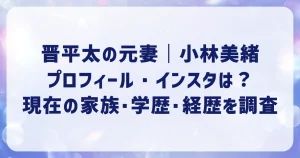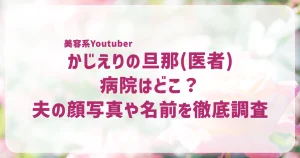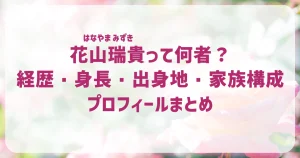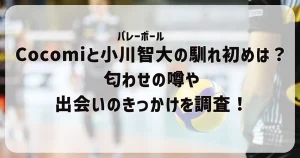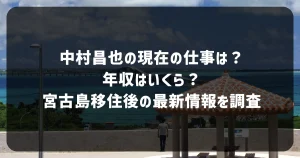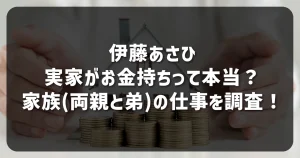「スーパー戦隊シリーズがついに終了する」というニュースが流れ、
「うそでしょ?」「時代が終わった…」と驚きと悲しみの声が広がっています。
1975年に放送が始まった『秘密戦隊ゴレンジャー』から50年。
子どもたちを夢中にさせてきた戦隊シリーズが、なぜ終了することになったのでしょうか。

「売上低迷」「少子化」「制作費の高騰」などが理由とされていますが、
実はそれだけでは語れないもっと深い理由があるようです。
この記事では、スーパー戦隊シリーズ終了はなぜ?売上や視聴率よりも深い3つの理由をまとめます。
スーパー戦隊シリーズ終了のニュース内容まとめ
関係者のコメントとして「制作費が見合わない」「関連グッズの売上が落ちている」とのこと。
ただ、東映やテレビ朝日など制作サイドからの正式発表はまだありません。
SNSでは、
「スーパー戦隊が終わるなんて信じられない」
「子どもの頃のヒーローがいなくなるの、寂しいな…」
といった声が相次いでおり、ファンの間に大きな衝撃が広がっています。
50年の歴史がひと区切りを迎えることになりますね。
スーパー戦隊シリーズ終了|売上や視聴率よりも深い3つの理由とは?
結論から言うと、スーパー戦隊シリーズが終わる背景には
売上や視聴率の数字だけではない、時代の変化とのズレがありました。
- 売上・市場の現実
- おもちゃ依存モデルの限界
- 子ども向けにこだわったことの難しさ



詳しくみていきましょう
① 売上・市場の現実
まずひとつ目の理由は、関連商品の売上の減少です。
2010年代前半には戦隊シリーズの関連グッズが年間100億円を超える売上を記録していましたが
近年は50〜60億円前後にまで落ち込み、
同じ特撮シリーズである仮面ライダー(約300億円)、
ウルトラマン(約200億円)とは大きな差が生まれています。
Yahoo!ニュースエキスパートも
「制作費の高騰や少子化などよりも、売上の低迷が最大の要因」と分析。
人気がなくなったわけではなく、ビジネスとして続けるのが難しくなったということですね。
② おもちゃ依存モデルの限界
2つ目の理由は、収益の仕組みそのものが時代に合わなくなったことです。
戦隊シリーズは長年、変身アイテムや合体ロボなどのおもちゃの販売が収益の柱でした。
ですが、今はYouTubeやスマホアプリなど、モノを買わなくても楽しめる世界に慣れています。
そのうえ、親世代も「毎年ロボを買い替えるのはちょっと大変…」と感じる人が増加。
人気があっても、視聴=売上に直結しにくい時代になってしまったのです。
③ 子ども向けにこだわったことの難しさ
そして3つ目の理由は、作品の方向性を変えにくかったこと。
仮面ライダーはストーリーを複雑にして大人も楽しめるように、
ウルトラマンは海外展開で幅広い世代に広がりました。
一方のスーパー戦隊は、あくまで“子ども向け”にこだわり続けてきました。
「昔ながらの良さを守るぶん、新しい層には届きにくくなった」という側面もあります。
まとめ
スーパー戦隊シリーズが終了する理由は、単なる売上や視聴率の問題ではなく、
「子どもたちに夢を届ける」という原点を守り抜いた結果だったのかもしれません。
半世紀にわたって、親子3世代に“仲間の大切さ”や“正義を信じる心”を伝えてきたこのシリーズ。
終わりを迎えても、その精神はきっとこれからのヒーローたちに受け継がれていくでしょう。